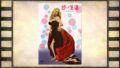お盆休み中の日本。
尤も、東京の下町では江戸時代までの旧暦七月十五日扱いでするところが多い。
現在の八月十五日とは何が違うのか。それは明治時代に政府が新暦への移行を決定し、それに従うように制定されたから。つまり旧盆と新盆の二種類が混在するようになった。
とはいっても、東京の七月は『新盆』で、全国的な八月のものが『旧盆』で、自分なんぞ、一ヶ月も早いのに「旧い」とは些かややこしいと感じるのは、意味をしらなかったからか。
同じく便利なのか統一なのか知らぬが、勝手にイメージとは違う改編が行われることも多い。
そのひとつが、昭和43年7月1日から施行された郵便番号制度。東京では旧町名が使用できなくなった。天下の銀座などでも一丁目から八丁目と実に味気ない。
現在の「銀座四丁目」交差点は、以前は『銀座尾張町』と信号機の下に書いてあったのを鮮明に覚えている。「ここが命の尾張町」なんてのも聞いたことがある。
それでも現新宿区や中央区の一部では旧町名を使用している地域もあり、実に羨ましい。「牛込箪笥町」とか「日本橋蛎殻町」なんぞ、憧れるね。
今や読めない人の方が多いだろうが、郵便番号制定以前は、例えば大体が一丁目単位で一町名であり、かなり覚えるのは大変だった。
でも、義務教育も受けられなかった小さな子供が丁稚や見習いとして仕事をする際に、嫌でも難しい町名で漢字を覚え、町名だけで頭の中に大体の地図が描けた。
これはある意味、生活に必要な知識、というか、不便さがもたらす嫌でもの学習効果だったのかもしれない。
そうやって合理的が浸透し、まったく疑わずに『便利だから』が常態化する。
だから自分は実家がある場所を、未だに「どこそこ何丁目」と呼ばずに旧町名で呼ぶ。
これは小学校時代の友人らも同様に旧町名で呼び合う。まあ、友人らは反骨精神ではなく、親兄弟がそう呼び続けてきた延長で特段意味もないか、時代の変化に対応できないだけかもしれないが。
残念なことに江戸前の落語が絶滅し、江戸弁は差別用語として扱われる。
その割には国営テレビでは江戸の吉原を舞台にしたものが放映されて、無邪気な若い女性たちが観光で訪れる。
良い時代になったもんだ。個人的には、あの治安の悪かった頃に酔っ払って迷い込んでも、冷静さを保たないと身の危険を感じたころが懐かしい。
何たって、もう40年も前のことだが素知らぬ顔で吉原迷宮に入り込んで歩いていたら、突然、通りの反対側から自分の名字を呼ぶ声がした。
まさか、こんな場所で大声で自分が呼び止められることなど絶対にない、と。
ゆっくり歩いていっても呼ぶ声が付いてくる。素知らぬ顔で周囲を見回すとボーイ姿の小学校時代の同級性が大きく手を振っていた。
確か、あ奴はヤクザになったんだよな、と思いながら何だよと近付いていくと「久し振りじゃん」と立ち話になり、まっすぐ帰れよと笑われたっけ。
これも地元のあるある話かも。でも、そ奴とは十年後ぐらいに銀座の高級クラブが立ち並ぶ「並木通り」を歩いていた時に、また向こう側の舗道から声を掛けられた。
その時は黒服姿だった。懐かしくて歩み寄っていき、あれお前ヤクザじゃなかったっけと尋くと、嬉しそうに「一応、カタギになった」と抜かしやがった。
だが、実はクスリをやっていて、更に十年後ぐらいに自ら命を絶った。
旧盆に思い出す話じゃないかもな。
でも、家族もいなかった奴だ。せめて自分ぐらいは思い出してやろうじゃないか。